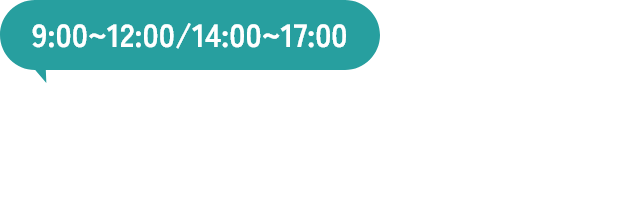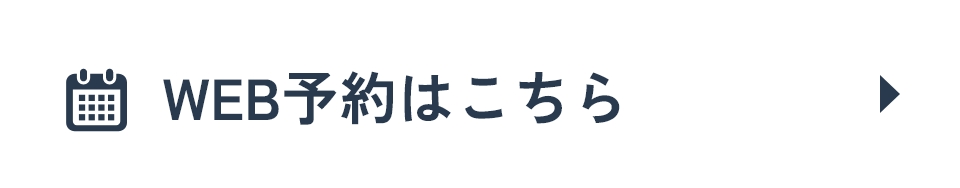病院受診のきっかけは?
やっと待ちに待った秋が来ましたね!あっという間に過ぎてしまいそうですが…
今回のテーマは「どんなときに病院にいけばいいの?」です。
病院に行くきっかけは2つです。
①気になる症状があるとき
②症状はなにもないけれど、健診・検診で受診を勧められたとき
①はわかりやすいですね。
消化器内科ならば、「おなかが痛い」「便秘」「下痢」「胸焼け」「便に血が混じる」、循環器内科ならば「動悸がする」「胸が痛い」「息が苦しい」などがそうです。
軽いものであれば病院に行かなくても自然によくなることもありますが、症状が強いときや長く続くときは、病院に行って薬をもらったり検査をするべきときです。
②は重い腰があがりにくいきっかけです。
症状があるわけではないので、病院に行くのが面倒だと感じることが多いと思います。でも、全ての病気に症状があるわけではなく、症状が出る前に対応した方がいいことがあります。
消化器内科だと「肝機能障害」「ピロリ菌陽性」「バリウムの検査異常」「便潜血陽性」などがこれに当たります。循環器内科ならば「血圧が高い」「心電図異常」「レントゲン異常(心拡大)」などを指摘されたときに、心臓の病気の可能性があります。
『未病』という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは、「病気まではいかないけれど健康を失いつつある」という東洋医学の考え方です。「健康」と「病気」は、くっきり2つにわかれているのではなく、グラデーションでつながっていて、『未病』の状態で対処していくことが大事なのです。「血圧高め」「コレステロール高め」などはまさにそうですね。健診ではこの状態だとC判定になることが多いと思われます。『未病』であれば、食事や運動などの生活の改善で「病気」になることを防ぐことができます。これを一次予防といいます。
健診でD判定が出ると、病院に受診しないとまずいかなぁと思われますよね。D判定では、多くの場合なんらかの診断がつきます。健診がきっかけで診断されることの多い、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、肝機能障害、どれも診断時には無症状のことが大半です。これらの病気を無症状のうちに見つけて早めに管理することで、次の重大な病気(心筋梗塞や脳梗塞、腎不全や肝硬変など)の発症を防ぐことができます。重大な病気とは、それが死因となりうる病気で、生活の質や寿命に関係してくるものです。それらに進行するのを防ぐことを、二次予防といいます。
さらに、早い段階の癌もほとんどが無症状です。胃がんも肝がんも膵がんも「早期」の段階では、なにも症状が出ません。がんが原因で自覚症状が出たときには、進行がんであることが多いです。それを早い段階のうちに見つけるのが健診・検診の重要な役割です。
健診の血液検査項目の異常は、どこ病院の何科を受診したらいいのか迷うこともあるかもしれません。答えは「どこの内科でも大丈夫」です。まずは近くの内科を受診して調べてもらい、専門的な検査が必要となれば、適切な病院へ紹介状を書いてもらえます。
気になる症状があるときは、些細なことでもいいので、なんでも相談してくださいね。健康に関するもやもやは、医師に伝えてすっきりするだけでも少し元気になれますよ!!